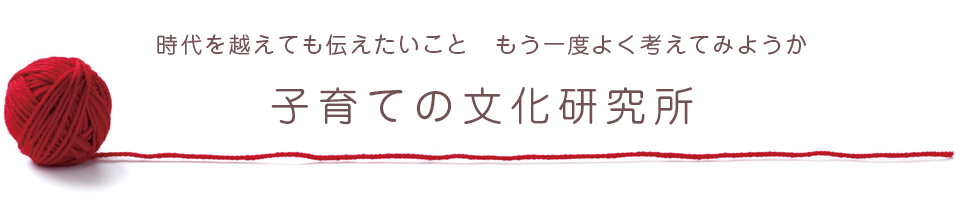子育ての文化研究所って?
「子育て」と言う行為は、親だけの責任では無いということが、この10年程で、ようやく社会全体で共有されるようになりました。身内以外からの支援が必要だ、地域ぐるみで子育て支援を、という雰囲気も拡がってきました。行政側の「つどいのひろば」をはじめとする様々な施策が功を奏し、随分、親が乳幼児を連れて出かける場所が増加すると共に、子育て支援のプログラムも増加してきました。
しかし、乳幼児に対する虐待のニュースは相変わらず続いています。最近になり、虐待とは無縁であっても、泣く我が子を受け止められない親、子育てが不安で不安で仕方ない親、自分の手だけで我が子を抱けない親(抱っこひもがないと不安)など、さまざまな問題を抱える親たちの現状を見聞きすることが多い私たちです。
このような現状の原因を考える時、子育ての方法が分からない親が増えていることが理由に挙げられるでしょう。子どもの頃から、乳幼児のお世話をしたこともなく、一緒に遊ぶ経験もないまま、我が子を育てることになってしまった親たち。不安は当然です。また、子育ての方法を世代から世代に伝えてこなかった社会、伝統として親が受け継いできた日本の子育ての文化を、母から受け継がないまま子育てしている母親が多いことも一因であるとの考えに至りました。
わたしたちは、この現状に立て直していく必要性を感じ、次の2点から、これらの問題を解決に導きたいと考えています。
(1)日本で伝統的に行われていた子育ての文化を掘り下げ、見直し、親たちにその良さを伝える。
(2)今の社会にマッチした子育ての在り方をまとめ、現状に対応できる子育て支援者を育成する。
販売中の講座
スクールのレビュー
-
2回目の視聴になりましたが、良い学びになりました。 今回はこのような形で、自分のペースで視聴出来たこと、ありがたかったです。 赤ちゃんを抱くときに「抱っこしますよ」「これでいいですか?」という声かけ、優しく触れるという触れ方、等、基本的な所からもう一度大切にしてやってみようと思います。 また 産後のお母さん達のケアについても、声かけが、できるところは寄り添いながらアドバイス出来たらと思いました。 子育てはいくつになっても子どもの発達が気になるものです。 発達は促す のでなく、見守る というところ。 という言葉がとても心に残りました。 そして、様々な 発達段階で様々な経験が出来るようにきっかけを作るのがそばにいる大人が出来ることかなと。一緒に楽しむ、というところ、その通りだなと改めて思いました。 最後に、吉田敦子さんの声のトーン、喋り方そのものが優しくて心地よかったです。ありがとうございました。
2025/2/15
-
赤ちゃんの抱っこは、目的に合ったものがあります。 色んな抱っこがありますが、赤ちゃんに、どうかな?気持ち良いかな?とお聞きしながら、調整するとお互いに気持ちの良い抱っこになります。 お腹の中から出でくると、6倍の重力を感じながら生活することになるので、練習の期間が必要です。 発達は応援するのではなく、見守るものなので、人と比べずる必要はありません。 赤ちゃんの力を信じて出来ないところは、どうしたらやりやすいかな? いま、どこまで出来ているのかな?と考えながら関わりましょう。 お家にあるタオルやおくるみを使って工夫することが出来ます。 授乳の時の抱っこも、フットボール抱きと言っても赤ちゃんの身体の向きや高さなど様々なので、楽に飲めるかな?と言う目線で考えると良さそうです。 心地良い抱っこは安心の場ですが、起きている時は身体を使って遊ぶことも大切ですので、そこもお伝えしたいです。
2024/12/9
オンラインで講座販売するなら


オンライン講座の開催/連絡/決済トータルサポート
無料ではじめる